スマートロックの危険性とは?対策方法と導入前の注意点を解説

スマートロックは、ハンズフリーで解錠・施錠ができたり、外出先から施錠ができたりする便利なアイテムです。
生活を豊かにしてくれる一方で、スマートロック本体の不具合やスマートフォンの充電切れなどで、解錠できずに締め出されたり、ハッキングされたりする危険性もあります。
この記事では、スマートロックに潜む危険性とその対策について、解説します。
スマートロックを導入したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
- スマートロックとは
- スマートロックの取り付け方法
- 貼り付けタイプ
- 穴あけタイプ
- シリンダータイプ
- スマートロックのメリット
- スマートロックの危険性
- スマートフォンの電池切れや紛失により締め出される危険性
- オートロック機能により締め出される危険性がある
- スマートロック本体の不具合により締め出される危険性がある
- 通信トラブルにより、締め出される危険性がある
- ハッキングされる危険性がある
- スマートロックの安全性を高める対策
- ハッキング対策されているスマートロックを選ぶ
- 故障やトラブル、締め出しに対するサポート体制があるか
- 電池切れを事前に通知してくれるスマートロックを選ぶ
- 物理的なカギを持ち歩く
- モバイルバッテリーを携帯しておく
- 複数の解錠方法があるスマートロックを選ぶ
- スマートロックを導入する際の注意点
- すべてのドアに取り付けられるわけではない
- 耐用年数がある
- 導入にはコストがかかる
- まとめ
スマートロックとは

スマートロックとは、スマートフォンやタブレットといった、モバイルデバイスにインストールした専用のアプリを使い、玄関ドアや門を解錠・施錠するシステムです。
カギ本体がなくても、解錠・施錠が可能で、一般住宅のほか、ホテルや民泊、レンタルスペースなど幅広く活用されています。
スマートロックの取り付け方法
スマートロックの貼り付け方法は、タイプによって異なります。
貼り付けタイプ、穴あけタイプ、シリンダータイプの3つのタイプ別に、貼り付け方法を解説します。
貼り付けタイプ
両面テープを使って、玄関ドアや門戸などに、スマートロックを貼り付けます。
工具が不要で、取り付けは容易にできますが、衝撃や雨などの影響で外れやすい点には注意が必要です。
玄関ドアや門戸を加工する必要がないため、退去時に原状回復を必要とする賃貸物件に適しています。
穴あけタイプ
玄関ドアや門戸など、スマートロックを取り付けたい部分に穴をあけて取り付けるタイプです。
貼り付けタイプと比較すると、外れにくいメリットがありますが、業者による工事や、工具を使っての作業が必要です。
また、穴があくため、原状回復が必要な物件には向いていません。
シリンダータイプ
ドアのカギ部分であるシリンダーを、スマートロックに交換します。
外れにくいメリットがありますが、穴あけタイプと同様、業者による工事や工具を使っての作業が必要です。
また、シリンダータイプのスマートロックのなかには、配線工事が必要な製品もあります。
スマートロックのメリット
スマートロックを導入することで、日常生活の利便性や防犯性が大きく向上します。
代表的なメリットは次のとおりです。
・外出先から施錠ができる
スマートフォンのアプリを使えば、離れた場所からでもドアの施錠が可能です。
鍵の閉め忘れに気づいても、その場で対処できます。
・物理的なカギを持ち歩く必要がない
スマホやICカードで解錠できるため、カギの紛失や忘れ物の心配がなくなります。
・防犯対策に役立つ
カギ穴がないタイプのスマートロックなら、ピッキングなどの被害も防げます。
侵入リスクを下げる手段としても有効です。
・ハンズフリーで解錠・施錠ができる
スマートフォンをポケットに入れたままでも、ドアに近づくだけで自動で解錠が可能です。
買い物帰りや子どもを抱えているときに便利です。
・締め忘れを防止できる
自動施錠機能を使えば、ドアを閉めたあと自動でロックがかかるため、うっかりミスを防げます。
・解錠・施錠履歴を確認できる
アプリ上で誰がいつドアを開けたか確認できるので、家族の帰宅状況や、不審な動きを把握しやすくなります。
スマートロックの危険性

スマートロックには、危険性も潜んでいます。ここでは、5つの危険性について解説します。
スマートフォンの電池切れや紛失により締め出される危険性
スマートロックの解錠・施錠には、主にスマートフォンのアプリを使用します。
スマートフォンに不具合や故障が生じたり、充電が切れてしまったり、紛失したりすると、スマートロックを解錠できず、締め出されるリスクが発生してしまいます。
オートロック機能により締め出される危険性がある
スマートロックのなかには、オートロック機能が備わっているものもあります。
カギやスマートフォンを室内に置いたままドアが施錠されると、外に締め出されてしまいます。
オートロックは、ドアを閉めてから自動施錠までの時間を設定することができます。
ドアが閉まったタイミングで施錠したり、スマートロックから離れると自動で施錠したり、お好みに合わせた設定が可能です。
スマートロック本体の不具合により締め出される危険性がある
スマートロック本体に不具合が発生すると、解錠や施錠ができなくなる恐れがあります。
室内にいる場合は手動で対応できるケースもありますが、外出中にトラブルが起きると、締め出されてしまう可能性もあります。
通信トラブルにより、締め出される危険性がある
停電時には、スマートロック本体とアプリやカードキーの間で、通信が不安定になることがあります。
また、スマートフォンを使っている場合、Wi-FiやBluetooth通信のトラブルにより、スマートロック機能に不具合が起きることもあります。
通信トラブルが起きた場合は、回復するまでスマートロックが使えず、通信が安定するまで待たなければならない恐れがあります。
ハッキングされる危険性がある
スマートロックは、Wi-FiやBluetooth通信を使い、サーバーと接続します。
ほかのインターネットを利用するシステムと同様、ハッキングされるリスクが伴います。
ハッキングの危険性はスマートロックに限りませんが、スマートロックがハッキングされることによる主なリスクを、例として2つ挙げます。
- 自宅に不正侵入されて、金品が盗まれる。
- 社内システムに不正侵入されて、機密情報が漏洩する。
スマートロックの安全性を高める対策

スマートロックの危険性を回避するために、安全性を高める対策を6つ解説します。
ハッキング対策されているスマートロックを選ぶ
窃盗や不正侵入などの被害に遭わないためにも、外部からの不正な攻撃を防ぐ、強固なセキュリティがあるスマートロックを選びましょう。
スマートロックのセキュリティ対策として、以下が挙げられます。
- ISMS/ISOやPマークなど、自社でセキュリティに関する認証を取得している
- データが暗号化されている
- 解錠に使用した信号が常に更新されるシステムを導入している
データの暗号化を導入しているスマートロックの中には、SSL通信による高度な暗号化を採用しているものもあります。
SSL通信は、金融機関でも採用されています。
故障やトラブル、締め出しに対するサポート体制があるか
スマートロックを長年使用する場合に、経年劣化したり、不具合が起こったりすることがあります。
故障やトラブルが発生した際に、修理や交換などの手続きがスムーズに進められるか、サポート体制が十分かを確認しましょう。
電池切れを事前に通知してくれるスマートロックを選ぶ
スマートロック本体の電池や充電が切れるとシステムが働きません。
スマートロックの中には、電池や充電の残量が少なくなると、アラームで通知してくれたり、スマートフォンでお知らせしてくれたりするものもあります。
また、メーカーによっては、サブスクで、自動で新しい電池を自宅に届けるサービスもあります。
物理的なカギを持ち歩く
万が一、スマートフォンやカードキーなどを持たずに外出してしまったり、スマートフォンの不具合などで解錠が難しくなったりしたときのために、物理的なカギを持ち歩きましょう。
カギの持ち歩きが難しい場合、自宅以外にカギを管理できる場所を確保しておくことが大切です。
オフィスでカギのかかるロッカーに預ける、信頼できる友人に預けるなどの方法が考えられます。
モバイルバッテリーを携帯しておく
モバイルバッテリーを携帯し、スマートフォンやタブレットの充電切れにより解錠できないリスクに備えましょう。
充電切れを防ぐために、外出時にはスマートフォンやタブレットを十分に充電しておくことも大切です。
複数の解錠方法があるスマートロックを選ぶ
スマートフォンアプリや暗証番号、指紋認証など、複数の解錠方法があるスマートロックを選びましょう。
スマートフォンの充電切れや紛失、暗証番号忘れなどが起きても、ほかの方法で解錠ができるため、大事には至りません。
スマートロックを導入する際の注意点
スマートロックを導入する際は、スマートロックの特性やコストについて考えなければなりません。
ここでは、3つの注意点について解説します。
すべてのドアに取り付けられるわけではない
スマートロックは、メーカーによって対応できるドアの種類が限られます。
例えば、専用機器の設置面が、平面でなければ取り付けられないスマートロックもあります。
また、ドアノブがあったり、プッシュプルハンドルであったりすると、取り付けできない場合があります。
耐用年数がある
スマートロックの耐用年数は、機器によって異なります。
耐用年数の差により、保守費用やメンテナンスの手間が異なるため、購入前に耐用年数を確認しましょう。
メーカーが定める耐用期間や保証期間前に、故障やトラブルなどが発生することも考えられます。
故障やトラブルが発生した際の対応についても、事前に確認し、必要に応じて対策を進めておきましょう。
導入にはコストがかかる
スマートロックの導入には、本体の購入や初期工事などの導入費用、運用費用がかかります。
メーカーや搭載している機能により異なりますが、本体の料金相場は、1~5万円ほどです。
ドアのスタイルによっては、スマートロックの設置工事が必要です。なお、レンタル型のスマートロックは本体の購入費用は不要ですが、レンタル料金がかかります。
まとめ
スマートロックの危険性として、締め出しやハッキングによる不正侵入などが挙げられます。
スマートロックは、セキュリティ対策が十分になされた、サポート体制が充実したものを選びましょう。
スマートロックの購入を検討されている方は、「トレテク!ソフトバンクセレクション」がおすすめです。
ソフトバンクの創業事業である『IT流通』を源流とするSB C&S株式会社が運営しているショッピングサイトのため、安心してお買い物が可能です。
豊富なラインナップから、自分の暮らしや好みに合った商品を選べますので、ぜひご利用をご検討ください。
詳しくは、商品一覧ページをご確認ください。
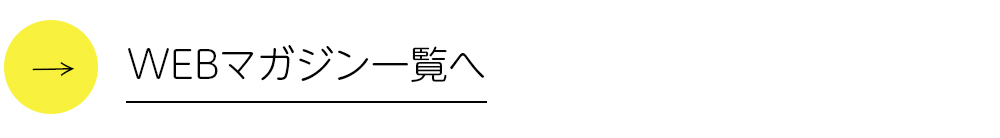








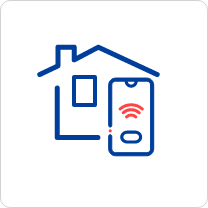

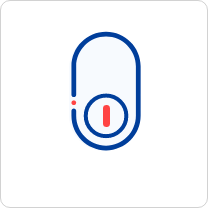

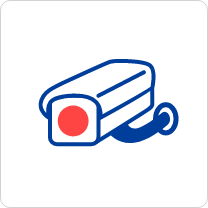

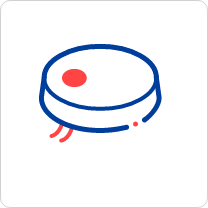

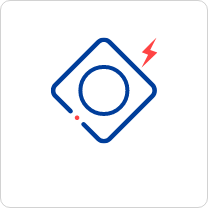

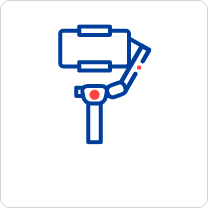

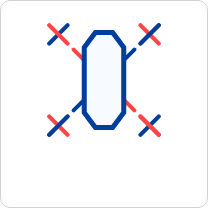
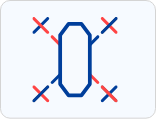
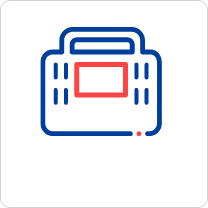

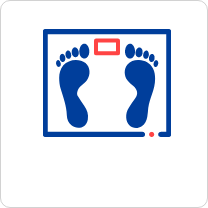

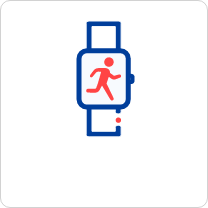

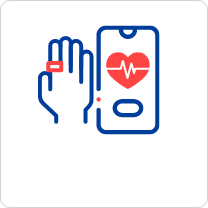

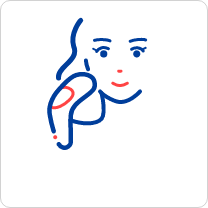
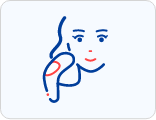
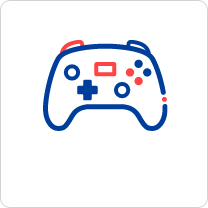



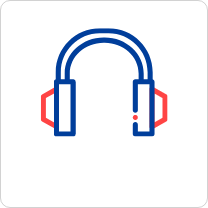

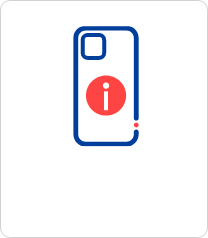

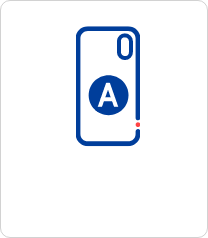

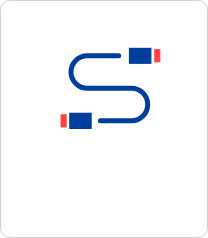

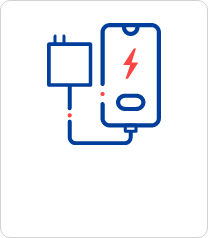
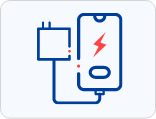
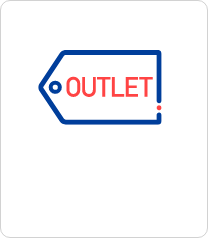


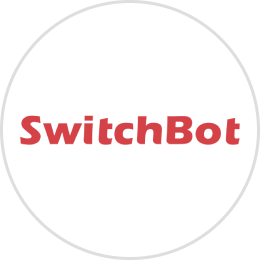














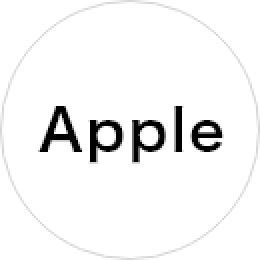












 ログイン
ログイン
 新規会員登録
新規会員登録